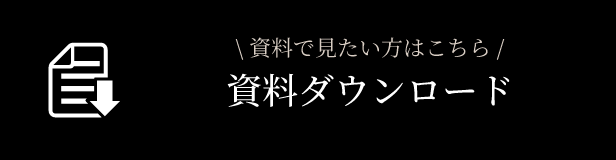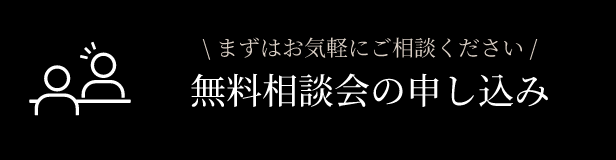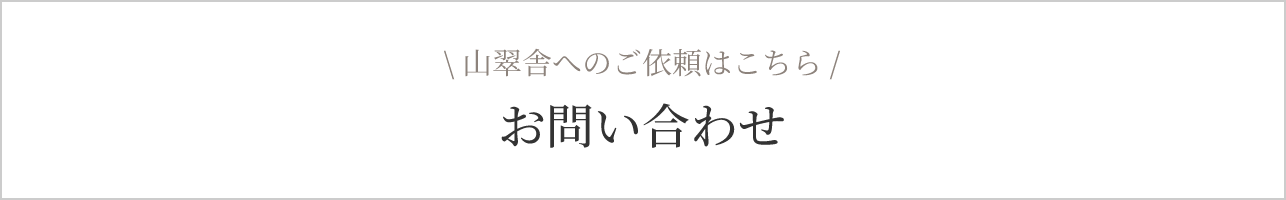日本の酒場のあり方を考える会社、酒場文化研究所。
同社が、江戸時代にあった居酒屋文化のエッセンスを今の日本で表現しようと、2021年2月にオープンさせたのが居酒屋「えんらい」です。
冷酒が当たり前になった時代に、日本酒のそもそもの姿だった燗酒の美味しさを再発見してほしい。同社代表の坂嵜透さんはそう語ります。
オープンから2ヶ月が過ぎた2021年4月、お店を訪ね、お話を伺ってきました。
(2021年4月4日 取材)
— 燗酒のお店なんですね?
そうですね。純米燗酒をメインにした居酒屋です。

— 酒場文化研究所というのは、このお店をやるために作られた会社ですか?
もう一つ、「純米酒三品」っていうお店もやってまして、この「えんらい」は2店舗目です。僕はほかにもJUKEJOINTっていう広告制作会社もやってまして、そこで広告ディレクターとかライターといった仕事をしてるんですけど、もともと自分がお酒好っていうのもあって、飲み歩いているうちに燗酒の魅力っていうものに出会ってですね・・・。
— いつぐらいのころですか?
もう20年ぐらい前、30歳過ぎたころなんですけど。それまでは、燗酒の魅力を知らなかったんです。
そのとき、自分が日本人でお酒が好きなのに、日本酒の本当の魅力っていうのを知らずに過ごしてきたっていうことが、すごくもったいないと思ったし、僕と同じような人が世の中にはたくさんいるだろうとも思ったんですね。
今も流行りは冷酒なわけで、それはそれでいいんですけど。 でも、もともとは歴史を辿っていくと、日本酒って燗酒で飲まれてたわけですから。

— そうなんだ。
もともとはそうですね。江戸時代の浮世絵とかに描かれている居酒屋の風景とかを見ても、お燗場があって、そういうスタイルで提供してたっていうのがわかるんです。
当然ながら昔は冷蔵機器とかがないわけで、今みたいに「冷やして飲んでくださいよ」っていうことはなかったわけで。 そうすると、日本酒の魅力っていうのは燗酒っていうところに本来のものが隠れているんじゃないかと思うんです。

— その燗酒の魅力っていうのは、具体的にはどういうものなんですか?
日本酒って、ワインとか果実酒ほど、ダイレクトに伝わる華やかな香りがあるわけではない。 お米の澱粉をもとに造られるものなので、直接的に刺激してくるような美味しさとかではなくて、もっと内に秘められたような美味しさがあると思うんですよ。だからお米本来の旨味とか味わいを引き出すには、温度を上げたほうが感じやすくなります。

ただ、歴史的に紆余曲折があって。 戦後の米不足のときに、日本酒の質っていうのが一気に悪くなったんです。いわゆる三増酒って言われるようなものが増えた。今でも醸造アルコールを入れたお酒のほうが、純米酒よりシェア率が高いと思うんですけど。
醸造アルコールどころか糖類とかを混ぜた粗悪なお酒が戦後に出回るようになって。 それで、日本酒の評価がどんどん下がっていった。 そういう時代のなかで、特に若い世代は日本酒に見向きもしなくなり、それとともに生ビールの流行で、飲みやすさ、喉越しの爽快さみたいなのが求められる傾向になってきたんです。
日本酒業界も「このままじゃダメだ、なんとかして売ろう」っていうことで、 「冷やして飲もう」っていうキャンペーンみたいなことをやったわけですよね。
今だと、吟醸酒とかで、ワインのような華やかな香りが引き出せるよう、そういう酵母を開発して、それを低温で発酵させて、できるだけ香りを引き出していくわけです。 その代わりに味わいを消していく。
香りを強調しながら、味はスッキリさせ、ライトな方向へと向かっていったんですよね。 もともと燗して飲んでたのに、冷やして飲む吟醸酒が王道になって。しかもそれを飲むのが「日本酒の通なんだ」みたいな方向に偏っていってしまったと。

なので僕も、燗酒の美味しさを知った時に、ショックを受けたんです。 それこそ、燗酒っていうのは毎日飲める。ご飯を食すように日常的に飲める。それが燗酒の魅力なんじゃないかなと思うんですよね。
まあそんなことで、自分も知らなかったから、そういう知らない人に燗酒を発見してほしいなと思って、酒場文化研究所っていう会社を作ったんですね。
あと、燗酒が美味しいと気づいたはいいけど、なかなか飲めるお店がないわけです。 それどころか、お酒にこだわったお店にかぎって「燗酒にしてもらえますか?」って言うと、「いいお酒だからお燗にするのはもったいないです」って諭されてしまうっていう(笑)。
なんかおかしな風潮に、どうにも我慢ができないと思って。 その思いが余って始めたのが「純米三品」っていう店だったんです。

— 「純米三品」を始められたのはいつの話ですか?
10年前、2011年の1月にオープンさせて。 でも、それは2年ちょっとで一回やめたんです。 さすがにシンドくなって。
— さすがに広告の仕事との二足のワラジでやるのはシンドい、ということですね?
それでやめたけど、なかなか日本酒への思いは断ち切れなくて。そうはいっても自分が表に立ってやるには限界がある。なので、今度は僕とは別に店長を立ててやろうと、2016年に道玄坂に「純米三品」を再オープンさせたんです。
小規模ワンオペの店舗ということで、僕としては副業的に再オープンさせたんですけど、ワンオペとなると、そこに立つ店長に依存するお店にどうしてもなりますよね。それで、もう一回原点に戻って自分のやりたいことをカタチにしようと思って今回開いたのが、この「えんらい」なんです。

— その原点っていうのは?
「江戸時代の居酒屋のエッセンスを再現するようなお店をやりたい」っていうことですね。 今も「角打ち」っていって、酒屋さんなんかが時々、お店の一角をお酒が飲めるスペースにして、っていうのがありますよね。
そもそも居酒屋の起源っていうのが、酒屋が軒先で飲ませたところから始まってるので、 そういう角打ちのような空気感を持った大人の酒場、ちょっと早い時間から一杯引っ掛けることができるような場所を作りたいなと。

そんなふうに思ってたときに、ここの物件が空いたので、この「えんらい」をオープンさせたんです。で、酒場文化研究所っていう社名にあるように、ただ飲み屋をやるっていうことではなくて、 そういった酒場の文化を発信して伝えていきたいっていうのがあるんです。例えば、酒器の販売とか、書籍の販売とかもやっていこうっていうので、物販と立ち飲みコーナーも作ったんです。
— なるほど。とても面白いですね。
— そういうお店の構想があって、それを山翠舎が施工することになったわけですが、山翠舎を選んだのにはどういった理由があったんですか?
同業からの紹介ですね。西荻窪に「カントニクス」というお店があって、そこの女将と日頃から仲良くしてたんです。で、「どこかいいところ知ってる?」って相談したら、山翠舎さんを紹介してくれて。
— 実際、どうでしたか?
まず僕がやりたいことをすごく的確に掴んでくれたんですよね。
— デザイナーさんは?
小林敬介さんです。 最初からすごく僕のイメージ通りの提案をしてもらって。ただ、予算が僕の方にあんまりなかったので、削れるところを少しずつ削っていって。
それでも結果的には予算をオーバーしたんですけど、せっかくいい提案をしてもらったので、できるだけその通り実現したいなっていう気持ちが勝りましたね。

— 入り口のこの作りは、外から中の賑わいがよく見えるように?
そうですね。開放的な感じにしたかったので。イメージは…、「魚三酒場」ってご存知ですかね?
東京の歴史遺産的な居酒屋として必ず出てくるような店なんですけど。紺色の重厚な暖簾がかかっていて、こういう引き戸をがらがらっと開けて入るような店なんです。とにかく「魚三酒場」みたいにしたいっていうのでお願いして、ほぼそのまま再現してもらった感じですね。
— これからこの「えんらい」で、どんなことを展開していきたいですか?
酒器とか書籍だけじゃなくて、食品の販売もやりたいなと思ってます。そもそも「えんらい」っていう店名をつけたのは、「遠くから来る」って書くんですけど。

— 「御遠来」ですね。
そう、御遠来(ごえんらい)。 遠い昔から受け継がれてきた日本人の知恵や生活文化というものを伝えられたらっていう思いがあって。それはお酒だけじゃなくて、食べ物もそうなんです。
今や料理もファストフード的な時短ブームで、今の都会の生活っていうのは、だんだんそういう方向になっていく、これは避けられないんでしょうね。
それでも、まだ田舎へ行ったら、おばあちゃんから代々受け継いでるような発酵食品があったり、その地に行かないと食べられないものがある。 やっぱりそういうものを知ると、昔からあるにも関わらず、すごく新鮮な発見になると思うんです。そうしたものにもっとスポットを当ててきたいなっていうのがあって、ちょっとずつ、 そういうものをここでも再現できて販売していけたらいいなあ、と思ってるんです。

— つまり地方に残っている伝統的な発酵食品、例えば奈良漬とかそうしたものを、「えんらい」が代理店となって販売していくっていうことですか?
代理店的に販売するものもあるし、自分たちで作ったものも売りたいんです。僕自身がそういう販売をしたいなと数年前から思ってたので、家で奈良漬を仕込んだり、ぬか床とか、長期熟成みたいなものもやったりしてきまして。
独学でやってるんですけど、それでも意外とカタチになるなあと。 まだまだ経験値が浅いので、そこを自分たちでも掘り下げていって、発信していけたらいいなあと思ってるんですね。
— 今日はありがとうございました。